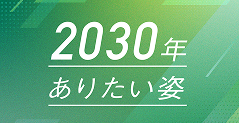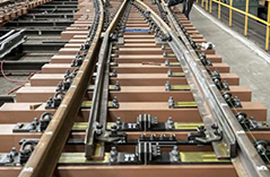リスクマネジメント
基本的な考え方
当社グループは、企業活動を取り巻くさまざまなリスクに対し、予防から収束まで適切に対応することが、社会的責任を果たし、信頼向上に資するとともに、「2030年ありたい姿」の実現に寄与すると考えています。潜在的リスクの予防に注力するリスクマネジメント活動においては、グループ各社の自主性や主体性を尊重することを活動の基本としています。不測の事態が発生した場合でも、不都合な情報が現場から迅速に伝えられる「BAD NEWS FIRST」の姿勢を徹底します。風通しの良い風土を醸成し、迅速・適切に対処することが、リスクの回避とともに、当社グループへの信頼を構築する礎になると考えています。
当社が認識している事業等のリスクは、有価証券報告書「事業等のリスク」をご覧ください。
体制
当社グループのリスク管理体制は、「リスクマネジメント基本方針」と「経営危機管理規程」が基礎となっています。「リスクマネジメント基本方針」は、リスクマネジメント活動の推進に関する基本的な方針と役割を定めたもので、「経営危機管理規程」は、不測の事態が発生した場合の具体的な対応を定めたものです。同方針や規程に沿って、グループ各社におけるあらゆるリスクの未然防止と危機発生時の損失最小化および早期回復に取り組んでいます。
大和工業取締役会を頂点とするグローバルで統合的なリスク管理体制を構築しており、同取締役会がグループ全体のリスク管理体制の統括責任を担っています。グループ各社の役員および社員は日々の事業活動の中でリスクに目を配り、潜在的なリスクの識別・評価、適切な対応・改善、モニタリングに注力しています。
不測の事態が発生した際には、グループ各社の代表取締役社長を本部長とする対策本部を速やかに設置し、情報連絡チームおよび顧問弁護士などを含む外部アドバイザリーチームと連携し、対応します。このように、損害の拡大を防止し最小限にとどめる体制を整備しています。
当社グループは、グループ横断的なリスクや潜在的リスクへの対応強化、さらなるリスクマネジメントの高度化とノウハウ蓄積を図るため、2023年7月、リスクマネジメント専門組織であるリスクマネジメント部を新設しました。そのうえで、当社グループが掲げる「2030年ありたい姿」の実現に向けてリスクの識別・評価、適切な対策を講じる活動を推進しています。これらの活動内容は、好事例も含めて大和工業経営会議等へ適宜報告され、社外取締役を含む経営層からのフィードバックを通じて、実効性のある継続的な改善につなげています。また、部の発足以降に実施してきた取り組みをマニュアル化し、自主的かつ継続的に実行可能なリスクマネジメント体制の構築に努めています。
BCP(事業継続計画)の取り組み
当社グループは、災害対応に関する規程を定め、有事の際に迅速に行動できる体制を整備しています。ヤマトスチール安全環境管理部の主催による火災や地震を想定した各種訓練を定期的に実施することで、災害対策の実効性確保を図るほか、2024年4月には、新たに安否確認サービスを導入し、災害時の通信手段の確保や迅速な情報収集体制の強化を図っています。また、安否確認にかかる訓練を定期的に実施することで、防災意識の向上にも努めています。実際に異常現象が発生した際は、人命の保護・救出、事業活動の早期復旧、社会的信用の維持を最優先に、被害を最小限に抑えるための防災本部を設置し、対処することとしています。
リスクカルチャー醸成に向けた取り組み
当社グループは、全ての社員がリスクマネジメントを自分ごととしてとらえ、継続的かつ日常的に取り組む企業風土を醸成することこそが、リスクマネジメント活動の推進に不可欠であると考えています。そのため、重要な施策の一環として教育・研修を位置づけ、リスクマネジメントの目的と役割の浸透に取り組んでいます。 2024年12月に、グループの経営層・管理者層を対象に外部講師を招いたリスクマネジメント研修を実施し、約80名が参加しました。経営層向け研修では、企業価値向上とリスクマネジメントの関係性や、当社グループのリスクマネジメント活動方針について理解を深めるとともに、今後注視すべき潮流や、開示情報の動向について分析を行いました。管理者層向け研修では、リスクマネジメント活動を推進する上で必要な視点や、推進役を担ううえで求められる行動について理解を深めました。受講者からの研修の評価は高く、全体で7割を超える満足度を得た一方、リスクマネジメントに対する理解度のばらつきや実務への適用における課題が明らかになりました。今後も、研修対象者の拡大や、役割に応じた研修の実施を通じて、実効性のあるリスクカルチャーの醸成・定着に取り組んでいきます。

リスクマネジメント研修の様子